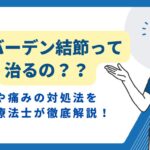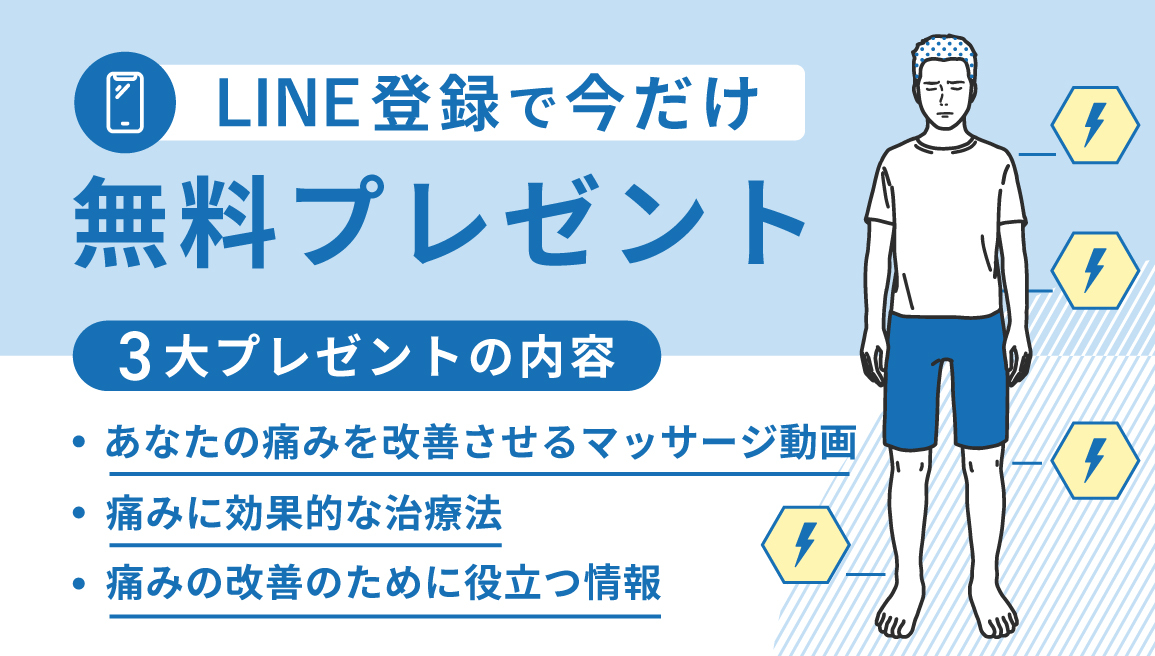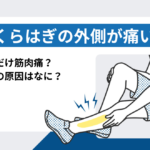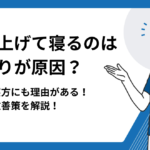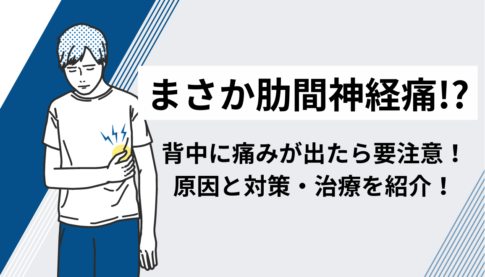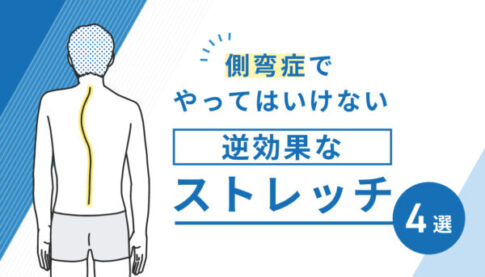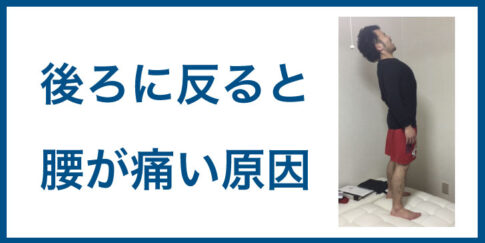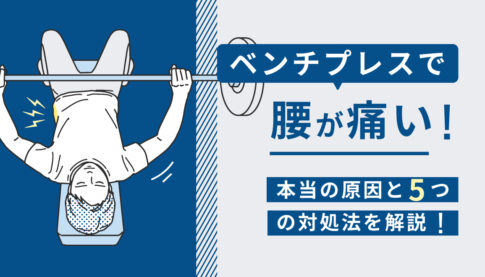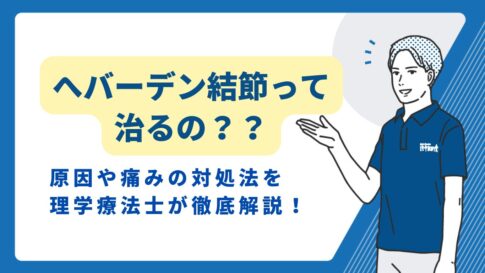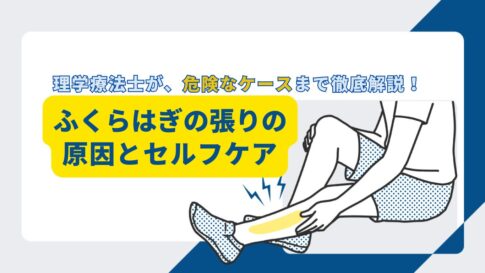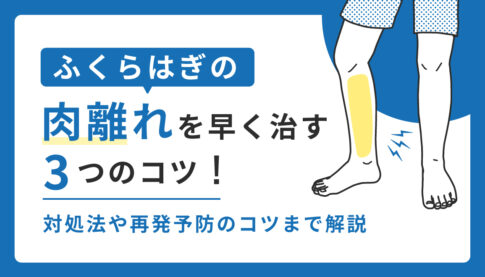坐骨神経痛で、やっていはいけないことがあるのはご存知ですか?
坐骨神経痛とは、腰から足先にかけて痺れや痛み、違和感などが生じる症状のことです。
「下半身の痺れがつらい」「腰から電撃のような痛みを感じる」
などの症状がひどくなると、次第に立つこと・歩くことさえも困難になってしまいます。
そんな坐骨神経痛でやってはいけないことは、
- 重たいものを持ち運ぶ
- 過剰にストレッチをする
- 全く動かさなくなる
- 激しい運動
- 長時間同じ姿勢で過ごす
- 体重の増加
の大きく6つです。ただこの6つを避けるだけではなく、その理由も合わせて確認しておくことが重要です。
本記事では理学療法士の目線から、坐骨神経痛でやってはいけないことの理由と注意点、さらに悪化を予防する対処法としてストレッチの具体的なやり方を、わかりやすく解説していきます。
目次
坐骨神経痛でやってはいけないこと6つ
坐骨神経痛でやってはいけないことは以下の6つです。
- 腰へ負担がかかる物の運搬
- 過剰にストレッチをする
- 全く動かさなくなる
- 激しい運動
- 長時間同じ姿勢で過ごす
- 体重の増加
痺れや痛みなどの症状がある方が避けるべき6つについて、それぞれ具体的にみていきましょう。
1.重たいものを持ち運ぶ
1つ目は、腰へ負担がかかる「重たいものの持ち運び」です。
坐骨神経痛の原因に、以下のようなものがあります。
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症状
- 腰椎すべり症
- 腰椎の変性
重い荷物などを運搬することで、上記のような坐骨神経痛の原因とその症状が悪化してしまいます。
普段の生活で腰へ負担がかかる物の運搬は避けるようにしましょう。
もし避けられない状況の場合、股関節や膝関節から曲げて体勢を低くした状態で、腰への負担を分散させることが大切です。
また、重い荷物を持つ前には、自分の体調や状態も確認し、無理をしないことが重要です。
周りに坐骨神経痛であることを伝え、手伝ってもらうことも時には重要です。
やむを得ない場合は、小さな荷物を何度にも分けて運ぶ、サポーターを着用するなど、工夫をすることで体への負担を軽減できます。
2.過剰にストレッチをする
2つ目は、過剰にストレッチをすることです。
間違ったストレッチは、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、腰の骨の変性などを悪化させる可能性があります。
しかし坐骨神経痛の症状がある方は、慢性的に腰に痛みがあったり、腰や背中の筋肉の緊張が強いことが多いため、ストレッチは必須です。
ストレッチを行う場合は、医師やリハビリの先生に十分に確認したうえで行うようにしましょう。
また、痛みを感じない範囲で行うことが重要です。
ストレッチは、筋肉をほぐし、柔軟性を高めるために効果的ですが、無理をすると逆効果になります。
効果的なストレッチ方法を学び、正しいフォームで行うことを心掛けてください。
初心者や症状がひどい方は、特に無理をせず、少しずつ行うことをお勧めします。
3.全く動かさない
3つ目は、全く動かさないことです。
坐骨神経痛の症状がある場合、安静にすることは非常に重要です。
しかし全く動かさなくなることで、身体を支えるのに必要な筋力が低下したり、逆に筋肉が硬くなったりします。
また必要以上に安静にしても、坐骨神経痛の根本の原因を改善することはできません。
そのため、無理のない範囲で日常生活を送り、適度に身体を動かすようにしましょう。
特に、軽いウォーキングやストレッチなど、柔軟性を保つための軽度な運動を取り入れることが推奨されます。
痛みが強くないときは、普段通りの動作を心がけ、動かすことから得られるプラスの効果を意識しましょう。
4.激しい運動
4つ目は、激しい運動です。
激しい運動は、腰や背中の筋肉への負担が強くなります。
また筋肉だけでなく、腰周囲の靭帯や椎間板などへの負担も強くなります。
そのため、坐骨神経痛の痺れや痛みを悪化させてしまう可能性が高いでしょう。
坐骨神経痛の症状がある方は、激しい運動は避けて無理のない範囲で動かすことが重要です。
特に、ジャンプや急激な動作を伴う運動は避けるようにしましょう。
運動を始める前には専門家に相談し、どの程度なら運動してよいのか、症状に合った運動方法を相談してみましょう。
5.長時間同じ姿勢で過ごす
5つ目は、長時間同じ姿勢で過ごすことです。
長時間同じ姿勢が長く続くと、腰周囲から足にかけての血液の循環が悪くなります。
また、長時間同じ姿勢で過ごすことで、特定の部位に負担がかかり、椎間板(骨と骨の間にあるクッション)への負荷も強くなり、骨の変性にもつながってしまいます。
そのためこまめに体勢を変えたり、適度に体を動かしたりして身体にかかる負担を分散させましょう。
特にデスクワークや長時間の座位が続く場合は、定期的に立ち上がり、軽いストレッチを行うことが重要です。
身体への負荷を軽減し、筋肉や神経を保つためのポイントを意識することで、坐骨神経痛の症状を和らげる助けとなります。
日常生活の中での小さな工夫が、長期的には大きな違いを生むことになります。
6.体重の増加
6つ目は、体重の増加です。
体重が増加すると、腹部に脂肪が蓄えられるため反り腰になりがちです。
また身体が重だるく感じることも多くなり、日常生活で運動量が減ってしまう傾向にあります。
身体への負担を軽減させるためにも、体重が増加しないよう食事などの生活習慣を意識することが大切です。
特にバランスの取れた食事や適度な運動を取り入れることで、体重管理を行うことが予防につながります。
また、体重を減らすことが難しい場合でも、少しずつ生活習慣を見直すことで、将来的な改善が期待できます。
坐骨神経痛の人がやるべきストレッチ・体操 ※動画で解説
坐骨神経痛の痛みをやわらげる簡単な体操とストレッチは以下の3つです。
- 梨状筋のストレッチ
- 坐骨神経のモビライゼーション
- 臀筋のトレーニング
①・②は座って行うもの、③は寝ながら行うものです。継続できるものから、ぜひ実践してみましょう。
これらのストレッチや体操は、特に坐骨神経痛による圧迫感や緊張を和らげるために効果的です。
日常生活の中で取り入れることで、筋肉の柔軟性を改善し、痛みの軽減が期待できます。
※いずれも痛みのない範囲で行いましょう。
梨状筋のストレッチ
梨状筋のストレッチの方法は、以下のとおりです。
- 椅子に浅く座り、片足であぐらをかく姿勢をつくる
- その足を手で押し込みながら、ゆっくりと上半身を前方へ倒す
- 呼吸を意識しながら、15〜30秒ほどキープ
- 逆足も同様に行う
このストレッチは、特に梨状筋が硬くなって坐骨神経を圧迫している場合に効果的です。
息を止めずに、無理のない範囲で行うことが重要です。痛みを感じない程度で実施しましょう。
ストレッチ後は、筋肉の緊張がほぐれている感覚を実感できるかもしれません。
坐骨神経のモビライゼーション
坐骨神経のモビライゼーションの方法は、以下のとおりです。
- 椅子の端に座る
- 外側の足の膝を伸ばし、つま先を上に反らすように足首を背屈させる
- その後膝を曲げて、つま先を伸ばすように足首を底屈させる
- リズミカルに②と③を、痛みのない範囲で繰り返す
この運動は、坐骨神経の動きが改善され、痛みの軽減が期待できます。
無理のない範囲で行うことが重要ですので、痛みを感じた場合はすぐに中止するようにしましょう。
また、座っているときは常に背筋を伸ばし、姿勢に気を付けることも効果的です。
お尻の筋肉(臀筋)のトレーニング
寝ながら行える臀筋のトレーニング方法は、以下のとおりです。
- 横向きになり両膝を曲げる
- 上側の膝を天井に向かって開く
- ゆっくりとおろす
- 逆側も同様に行う
上側の膝を開くときに、お尻が後ろに倒れないように注意しながら行います。
このトレーニングは、お尻のインナーマッスルを強化し、腰や股関節の安定性を高める効果があります。
普段使いにくいお尻のインナーマッスルを鍛えることで、姿勢改善にも繋がります。
無理をしない範囲で繰り返すことがポイントです。
トレーニング中に痛みを感じた場合は、すぐに中止するようにしましょう。
継続的に行うことで、臀部の筋力が向上し、坐骨神経痛の症状緩和にもつながります。
そもそも、坐骨神経痛って?
坐骨神経痛は、疾患名ではなく腰から足先にかけて痺れや痛みなどが生じる症状の総称です。
坐骨神経は、身体にある神経のなかでいくつもの神経が収束してできた最も長くて太い神経です。
その坐骨神経が何らかの原因で圧迫されることによって、痺れや痛みなどの坐骨神経痛の症状がみられます。
坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など、さまざまな疾患に関連しています。
これらの疾患が神経を圧迫することで、下肢に痛みやしびれとして現れるのです。
坐骨神経痛の症状は、ももの裏からふくらはぎにかけて強い痛みが走ることが特徴であり、ひどい場合は立つことや歩くことすら困難になることもあります。
このような症状が続くことで、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
したがって、坐骨神経痛の原因を理解し、それに基づいた対処法を身につけることが重要です。
坐骨神経痛の原因【4つの病気】
坐骨神経痛には、原因となる病気があります。
その原因となる病気は、以下のとおりです。
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰椎すべり症
- 梨状筋症候群
それぞれ解説します。
坐骨神経痛の原因①:腰椎椎間板ヘルニア
1つ目の病気は、腰椎椎間板ヘルニアです。
腰椎椎間板ヘルニアは、背骨を構成している椎体と椎体の間にある椎間板という軟骨が、腰椎にかかる負担によって飛び出したり、はみ出したりすることで神経を圧迫します。
それによって坐骨神経を圧迫し、坐骨神経痛を引き起こす可能性があります。
腰へ大きな負荷がかかるような重い荷物を持ったり、長時間前かがみや中腰などの姿勢を続けたりすることで、発症リスクが高くなります。できるだけ避けるようにしましょう。
また、過度の運動や姿勢の悪さもリスク要因です。
腰椎椎間板ヘルニアは、特に若年層から中高年まで広く見られる疾患で、早期の治療が重要です。
症状が悪化する前に、専門医の診断を受け、適切な対策を講じることが、改善の第一歩となります。
坐骨神経痛の原因②:腰部脊柱管狭窄症
2つ目の病気は、腰部脊柱管狭窄症です。
背骨の中を通っている脊柱管が、なんらかの原因で狭窄されて神経を圧迫します。
その圧迫によって、坐骨神経痛の症状を引き起こします。
腰部脊柱管狭窄症の症状として、一定の距離を歩くと腰から足にかけて痺れや痛みを生じ、少し休憩すれば症状が治まってまた歩けるようになる間欠性跛行がみられるのが特徴です。
腰部脊柱管狭窄症は、加齢に伴った腰椎の変性が原因の場合がほとんどですが、脊柱管が生まれつき狭い場合もあります。
この疾患は、特に中高年層に多く見られ、日常生活に支障をきたすことがあります。
体幹の安定性を高める運動や姿勢の改善、適切な治療を行うことで、症状の軽減が期待できるため、早期に医療機関を受診することが重要です。
坐骨神経痛の原因③:腰椎すべり症
3つ目の病気は、腰椎すべり症です。
腰椎すべり症の原因は明らかになっていませんが、スポーツによる腰椎への負担や加齢によって、椎間板や靭帯、関節などの変性がすべり症につながるとされています。
腰椎のずれによって、その後方を通っている神経が圧迫されて坐骨神経痛の症状が生じます。
特に、ジャンプや激しい動きが多いスポーツを行う選手や、長時間同じ姿勢を保つ仕事をしている人にリスクが増える傾向があります。
腰椎すべり症の特徴的な症状として、腰の痛みや下肢の痺れなどがあり、動作や姿勢によって症状が変化することもあります。
この疾患もまた、適切な治療やリハビリテーションが重要で、早めの診断と対策が推奨されます。
坐骨神経痛の原因④:梨状筋症候群
4つ目の病気は、梨状筋症候群です。
おしりの深い位置にある梨状筋は、通常柔軟性のある筋肉ですが、長時間デスクワークなどで同じ姿勢が続くことによって負担がかかり、緊張が強くなります。
梨状筋症候群は、その梨状筋の過剰な緊張によって、その周囲を通っている坐骨神経が圧迫され、坐骨神経痛の症状を引き起こします。
特に、座った状態が長時間続く場合や、脚を組んでいる時間が長いことが影響することがあります。
この症状を改善するためには、定期的にストレッチを行い、梨状筋の柔軟性を保つことが重要です。
また、姿勢を意識的に改善することで予防にもつながります。
梨状筋のストレッチを行うことで、筋肉の緊張を緩和し、坐骨神経への圧迫を軽減する助けになります。
坐骨神経痛で注意するべき【日常の対策と予防法】
坐骨神経痛を予防するためには、まずは日常生活の中での姿勢や運動を意識することが重要です。
座りっぱなしや立ちっぱなしを極力さけ、適度な運動を行い、筋肉の柔軟性を保つことが痛みの軽減につながります。
また、荷物を持ち上げる際は膝立ちになるなど、腰を過度に曲げたり、反らしたりするのを避けましょう。
いつも以上の負荷がかかる時ほど、正しい姿勢を心掛け、腰に負担をかけないよう注意が必要です。
さらに、体重管理を行い、健康的な生活習慣を維持することで、坐骨神経痛のリスクを減少させることが可能です。
坐骨神経痛でやってはいけないこと【まとめ】
坐骨神経痛の症状を引き起こす原因はさまざまで、長時間同じ姿勢を続けたり、腰に負担のかかる動作を行なったりすることを避けるなどの対策が必要です。
また、適切なストレッチや体操を取り入れることで、筋肉の柔軟性を保ち、坐骨神経痛の緩和につながります。
理学BODYでは坐骨神経痛の原因となる筋膜へアプローチし、症状を根本から改善と再発の予防を行います。
もし病院や治療院へ通ってもなかなか症状が改善しない場合は、筋膜のプロである私たちに一度ご相談ください。
◾️こんな記事もおすすめ(腰の痛み・病気)
投稿者プロフィール

- 【青山筋膜整体 理学BODY WEB編集長】理学療法士歴10年以上 総合病院⇨介護・予防分野⇨様々な経験を経て独立。臨床で得た知識をもとに、書籍の執筆・WEB発信・東京都の高齢福祉事業など分野問わず活動中。

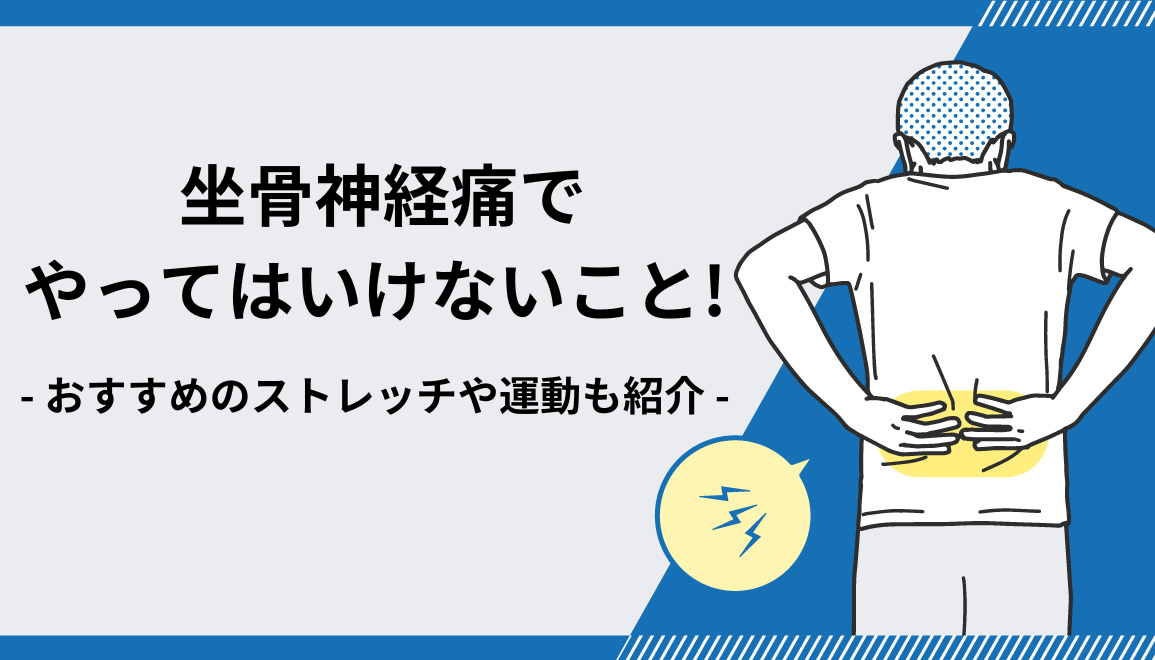
 木城先生
木城先生